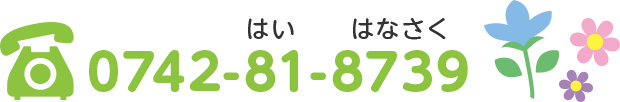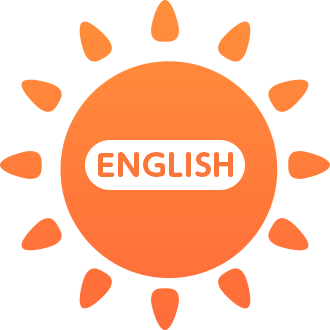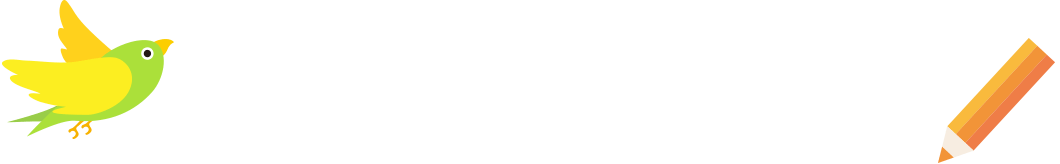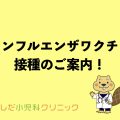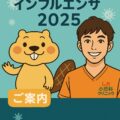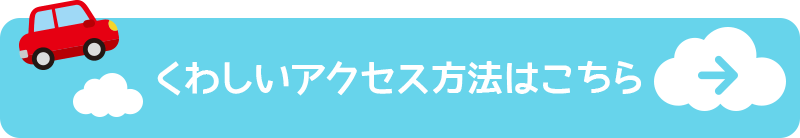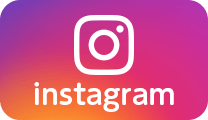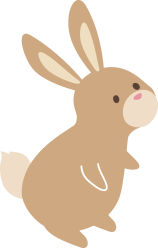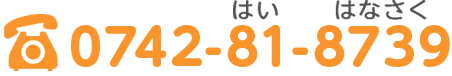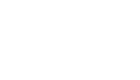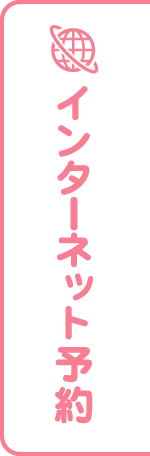2019.12.18
最終更新日: 2024年12月18日
接種を推奨します!インフルエンザワクチンについて
目次
はじめに
インフルエンザは、冬に流行するおなじみのウイルスです。
健康なお子さんの場合、自然に治ることが多い病気ですが、一方で肺炎やインフルエンザ脳症など、重症化することもあるため注意が必要です。
また、インフルエンザにかかると学校を休まなければならなかったり、何度も病院に通わないといけなかったりと、
ご家庭の負担も少なくありません。

お子さんの健康を守るためにも、ぜひワクチン接種をご検討ください。

よく耳にするこの疑問。
実際、インフルエンザワクチンを接種しても、残念ながら100%感染を防げるわけではありません。
では、どの程度効果があるのでしょうか?
インフルエンザワクチンの効果
インフルエンザワクチンは、次のシーズンに流行しそうなウイルスの「型」を予測し、
複数のウイルスを組み合わせて作られます。
そのため、毎年少しずつ違うワクチンが製造されているのです。
型の予測が当たった場合、ワクチンにはおよそ50~80%の予防効果があるとされています。
一方で、型の予測が外れてしまった場合でも、予防効果は下がりますが、重症化を防ぐ効果はしっかりと認められています。
また、6カ月未満の赤ちゃんやワクチン接種ができないお子さんがいる場合、周囲の方がしっかりワクチンを接種することで守ってあげることができます。
これは「集団免疫」と呼ばれる考え方で、非常に重要です。
ただし、インフルエンザワクチンは定期接種ではなく自費接種であるため、集団での接種が難しい現状もあります。
しかし、ご家族やお友達など、周りの人が一緒にワクチンを接種することで効果が高まることが証明されています。
大切なお子さんやご家族を守るためにも、ぜひみんなでインフルエンザワクチンの接種をご検討ください。
「毎年受けないとダメ?」
「毎年ワクチンを打つ必要があるの?」と思われる方も多いかもしれません。
残念ながら、インフルエンザワクチンは毎年接種が必要です。
その理由は大きく2つあります:
免疫が1年で下がってしまう
ワクチン接種によって得られた免疫は、時間が経つと徐々に低下することがわかっています。ウイルスが変化する
インフルエンザウイルスは毎年少しずつ変異するため、流行する型も変わることが多いのです。毎年ワクチンを作り直しているのはそのためです。
そのため、毎年ワクチンを接種することが大切となります。
「いつ受けるのが良い?」
インフルエンザは、例年12月から3月ごろに流行します。
そのため、その前にワクチンを接種しておくことが大切です。
おすすめの時期は10月から11月ごろです。
このタイミングで接種すれば、流行が始まる前にしっかりと免疫をつけることができます。
ただし、もし打ちそびれてしまった場合でも大丈夫です。
流行している時期(12月以降)でもワクチンを接種する意義はあります。
接種してから効果が出るまでには約2週間かかるため、
できるだけ早めの接種をおすすめします。
接種回数と間隔について
年齢によって接種回数が異なります。
- 生後6カ月~12歳: 2回接種
- 13歳以上: 1回接種
接種間隔は?
インフルエンザワクチンは「不活化ワクチン」ですので、1週間あければ2回目を接種することが可能です。
ただし、免疫効果を最大限に引き出すためには、3~4週間の間隔をあけるのがおすすめです。
(ちなみに、「生ワクチン」の場合は、1カ月間隔をあける必要があります
インフルエンザワクチンを打てない条件は?
不活化ワクチンとはいえ、体内に異物を注射するため、体調が良い時に接種することが大切です。
- 発熱(37.5℃以上)している時は、接種を避ける必要があります。
- **軽い風邪症状(鼻水や軽い咳)**程度であれば、接種しても問題ありません。
もちろん、体調がベストな時の方が望ましいですが、
あまり慎重になりすぎて接種時期を逃してしまうと、インフルエンザにかかるリスクが高まってしまいます。
次の方は接種ができないことがあります
- 過去にインフルエンザワクチン接種後、強い副反応(体調不良)があった方
- 重い卵アレルギーがあるお子さん(卵アレルギーについては後述します)
インフルエンザワクチンの副作用について
ワクチン接種後に起こりうる副作用には、軽いものから重いものまでありますが、重い副作用は非常に稀です。
軽い副作用
他のワクチンと同様に、以下の症状がみられることがあります:
- 接種部位の腫れ、赤み、しこり
- 発熱
重い副作用
ごく稀ではありますが、以下の重い副作用が報告されています:
- アナフィラキシー(急性のアレルギー反応)
- ギラン・バレー症候群(末梢神経の麻痺)
- 急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(神経に炎症が起こる病気)
アナフィラキシーに注意が必要な方
アナフィラキシーは、ワクチンに含まれる卵由来成分や添加物が原因となることがあります。
そのため、次の方は特に注意が必要です:
- 過去に卵アレルギーでアナフィラキシーを起こした方
- 以前にワクチン接種で強いアレルギー反応や体調不良があった方
接種が不安な場合は、事前にご相談ください。
卵アレルギーでもインフルエンザワクチンは打てる?
インフルエンザワクチンには、ごく微量ながら卵の成分が含まれています。
しかし、ほとんどの卵アレルギーの方にとっては問題にならないことが多いです。ただし、念のため注意が必要です。
当院での対応について
以下に該当する場合は、原則として接種できません:
- 過去にワクチン接種でアナフィラキシーを起こした既往がある方
- 卵を完全除去していて、加工品(クッキーやケーキなど)も一度も食べたことがない方
卵アレルギーがある場合でも、状況によってはワクチン接種が可能なことがほとんどです。
ご不安な方は事前にご相談ください。
同時接種は可能か?
結論から言うと、同時接種は可能です。
生後6カ月~2歳のお子さんに、肺炎球菌ワクチンや4種混合ワクチンと一緒にインフルエンザワクチンを接種した場合、
発熱や熱性けいれんが起こる率がやや高くなるという報告があります。
ただし、そのリスクは 10万人に30人程度 と非常に低い確率です。
当院の考え方
ワクチン接種のタイミングを逃してしまうことの方が、病気にかかるリスクを高めると考えています。
そのため、当院では積極的に同時接種を行っています。
もちろん、「同時接種が心配…」という場合は、
別々に接種することも可能ですので、ご希望があればお知らせください。
さいごに
私自身、研修医の頃にインフルエンザ脳症で患者さんを亡くした経験があります。
そのお子さんは卵アレルギーがあり、インフルエンザワクチンを打てていなかったのです。
当時の判断では仕方がなかったのでしょう。でも、もしあの時、ワクチンを接種できていたら、、、、?
その後も何例ものインフルエンザ脳症を経験してきましたが、
一度発症すると救命することすら難しく、完全に治るケースはごく稀です。
インフルエンザワクチンは、重症化を防ぎ、お子さんの命を守るための大切な手段です。
そのようなケースを少しでも防ぐように、ベストは尽くしておきたいと考えています。
接種をご希望の方は、お待ちしております。