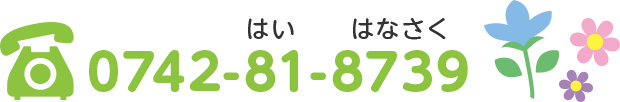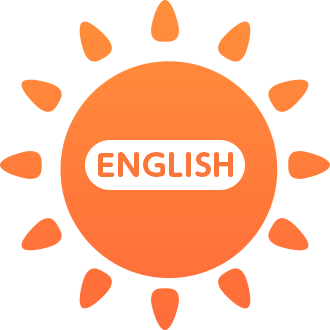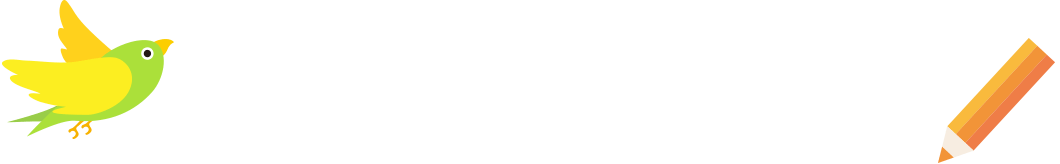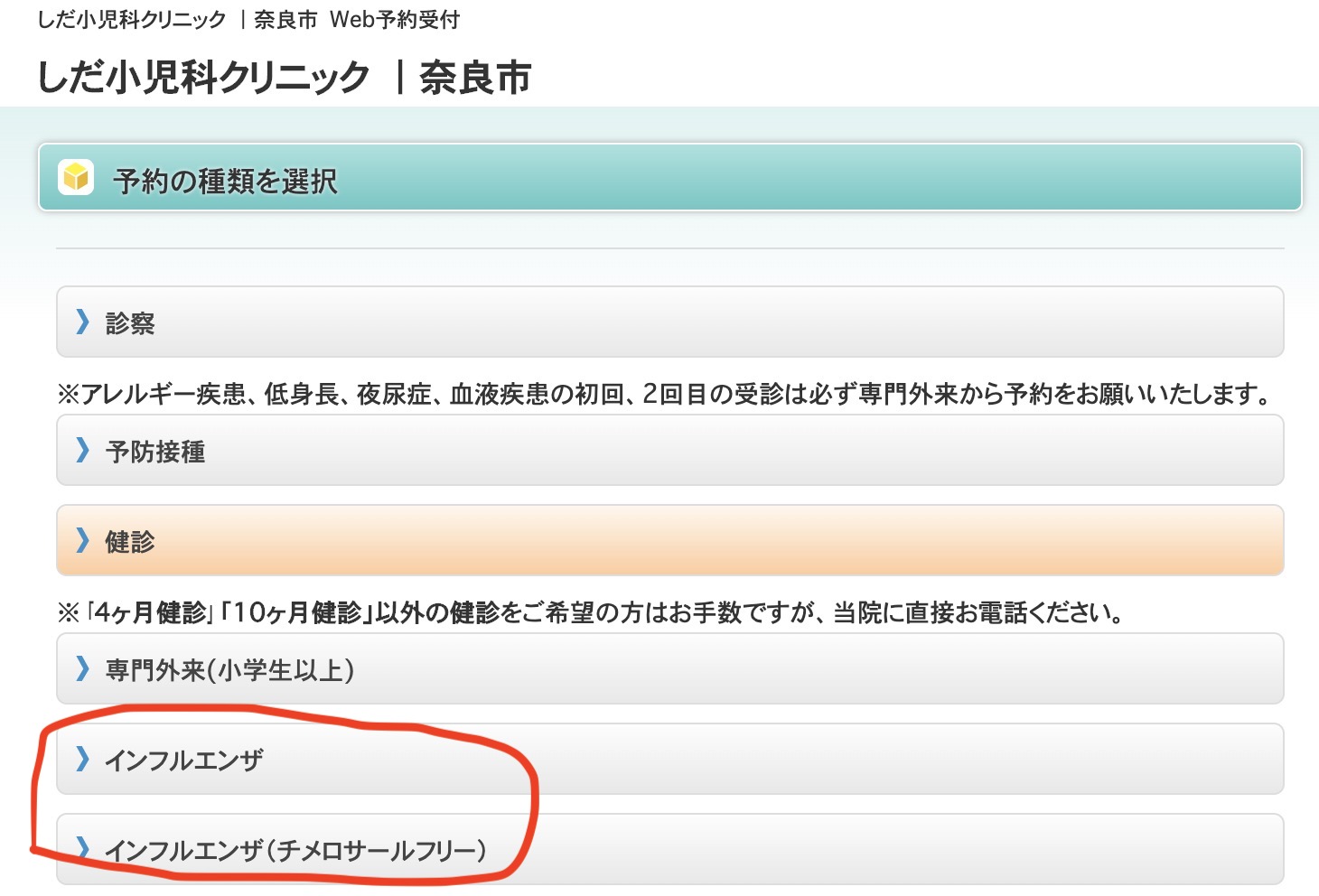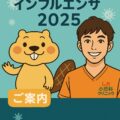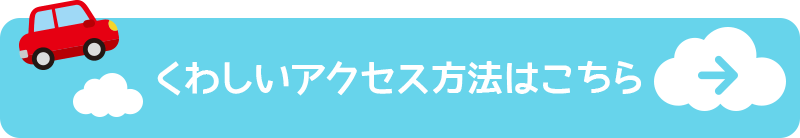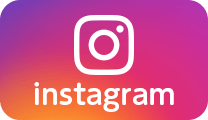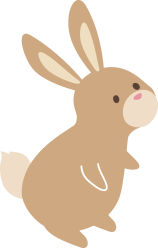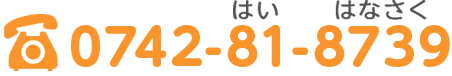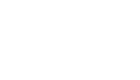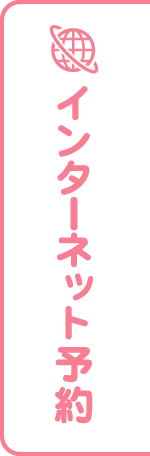2025.05.06
最終更新日: 2025年08月13日
小児喘息の治療、発作が治まったら終わり?
前回の記事では、喘息発作の急性期治療についてお話ししました。
吸入薬を使ってその場の症状を和らげることはとても大切ですが、
実はそれだけでは喘息は良くなりません。
喘息は、「気道に慢性的な炎症」が起こっている病気です。

今回は、この「目に見えない炎症」を抑えるための“長期管理”についてです!
目次
長期管理の目的は「発作を起こさせないこと」
喘息の長期管理は、単に症状を抑えるだけではなく、
発作の予防、そしてお子さんの生活の質(QOL)を守ることが目的です。
急性期治療と長期管理の違い
急性期治療:発作が起こったときに行う治療(気管支拡張薬など)
長期管理:発作を起こさせないために、毎日継続する治療
症状がなくても毎日薬を使う、ということに抵抗を感じる保護者の方も少なくありません。
できれば無駄な薬はつかいたくありませんね。

長期管理を怠るとどうなる?
喘息の長期管理を自己判断で中断したり、治療を怠ったりすると、次のようなリスクがあります。
1. 再発のリスクが高まる
症状がなくても気道の炎症は持続しているため、薬をやめると再び発作が起こりやすくなります。
発作が重症化すると、入院や命に関わることもあります
実際、長期管理が不十分な小児喘息では、1年以内に発作を再発するリスクが2倍以上になるという報告もあります。
2. 学校生活への支障
夜間や運動時の咳が続くことで、
体育や外遊びに参加できなくなったり、
睡眠不足や集中力低下を招くこともあります
未治療の喘息児の約40%が生活制限を経験しているというデータもあります。
3. 成長や発育への影響
慢性的な症状や夜間の咳により、
睡眠不足や活動制限が生じ、
成長や発育に悪影響を及ぼす可能性があります。
4. 肺機能の低下
子どもの時期にコントロール不良が続くと、
肺の発育が妨げられ、将来の肺機能が低下する可能性があります
5. 気管にダメージが残る(気道リモデリング):重症化・難治化
慢性的な炎症が続くと、気道の壁が厚く・硬くなり(リモデリング)、
治療薬が効きにくくなったり、大人になっても喘息が残る「難治性喘息」につながるリスクが高まります

症状がなくても炎症は残っているため、自己判断で治療をやめず、医師の指示に従って継続することが大切なんです
小児喘息の長期治療:第一選択は抗アレルギー薬

主に使用される薬剤
ロイコトリエン受容体拮抗薬(LTRAs)
ロイコトリエン受容体をブロックし、気道収縮や炎症を抑えます。
モンテルカストナトリウム(シングレア®/キプレス®)
プランルカスト水和物(オノン®)
Th2サイトカイン抑制薬
アレルギーの原因物質が出す「Th2サイトカイン」と呼ばれる信号(IL-4やIL-5など)をブロックし、気道の炎症を抑える内服薬です。
スプラタストトシル酸塩(商品名:アイピーディ®)
→ 少しマイナーな薬ではありますが、特に小児喘息において、症状悪化抑制や予防効果が報告されています。
これらの抗アレルギー薬は、毎日継続して服用することで、炎症のベースを抑える効果が期待できます。
副作用も少なく、特に初期の喘息症状や軽症例に適しています。
吸入薬について(概要)
吸入ステロイド薬(ICS)は、気道の慢性炎症を抑えるための重要な治療薬です。
内服薬に比べて全身への影響が少なく、小児喘息の中等度以上の管理では標準的な治療法のひとつです。
ICSは長期的に使用しても比較的安全とされていますが、副作用として以下のような点に注意が必要です:
主な副作用:口腔カンジダ(吸入後のうがいで予防可能)
全身性の副作用は極めて少ないとされていますが、長期使用ではまれに成長への影響が指摘されています(次項参照)
吸入ステロイド薬(ICS)は、気道の慢性炎症を抑えるための重要な治療薬です。
小児喘息の中等度以上の管理では、抗アレルギー薬だけで不十分な場合に吸入治療を併用することがあります。
主な薬剤は以下のように分類されます(※詳しくは別記事にて解説予定です)。
吸入ステロイド薬(ICS)
オルベスコ(シクレソニド)
フルタイド(フルチカゾン)
キュバール(ベクロメタゾン)
パルミコート(ブデソニド)
吸入ステロイド薬(ICS) + LABA 合剤(長時間作用性β2刺激薬)
吸入ステロイド薬(ICS)とLABA(長時間作用性β2刺激薬)を1つにした合剤は、1つの吸入器で気道の炎症と収縮の両方を抑えることができる薬です。
小児では重症例や中等症で他の治療ではコントロールが難しい場合に検討されます。
アドエア(フルチカゾン+サルメテロール)
フルティフォーム(フルチカゾン+フォルモテロール)
✔️それぞれに適応年齢や吸入デバイスの違いがあります。
➡️詳しくは「小児喘息の吸入治療ガイド」の記事をご覧ください。
吸入ステロイドの身長への影響について
ステロイドには成長障害の副作用があるのですが、具体的にはお子さんにとっては低身長が気になりますね。
**CAMP試験(Childhood Asthma Management Program)**という米国の大規模研究という研究がとても参考になります。
この研究によれば
吸入ステロイド薬(ICS)使用群とプラセボ(不使用)群を比較したところ、初期に約1〜1.5cmの成長抑制が見られたと報告されています。
しかし、その後の経過で最終身長には有意差がなかったとされています
むしろ、喘息の治療が不十分で「喘息発作を繰り返してしまうほうが成長に影響が出る」と考えられます。
もちろんステロイドを使いすぎたり、だらだら使用することは避けねばなりませんが、
最終的には喘息を適切にコントロールすることが、結果的に成長や発達を守ることにもつながります。
治療継続のコツ
喘息の長期管理は、一度治療を始めたら終わりではなく、症状の経過を見ながら内服薬やICSを適切に調整していくことが大切です。
治療の強さを変える際は、必ず医師と相談し、自己判断で中止したり減らしたりしないようにしましょう。
また、喘息の悪化要因としてよく見られるのが、感冒(風邪)やアレルギー性鼻炎の合併です。
風邪をきっかけに喘息が悪化することも多く、普段からうがいや手洗いの徹底、風邪をひいた際の早期治療が重要です。
アレルギー性鼻炎も喘息の症状を悪化させる原因となります。
抗アレルギー薬の使用に加えて、ダニやハウスダストなどアレルゲンの除去、生活環境の見直しも効果的です。
さらに、舌下免疫療法はアレルギー性鼻炎の根本治療として知られていますが、喘息症状にも改善効果が期待されることが複数の研究で示されています。
舌下免疫療法も当院では積極的に取り組んでいます。
ぜひご相談ください。
継続のポイントまとめ
症状がないときこそ、治療を続ける意味があります。
吸入や内服は、毎日同じ時間に行うと習慣化しやすくなります。
副作用が不安なときは、ご相談ください。
保護者とクリニックがチームとして、お子さんの健康を支える意識が大切です。
喘息の治療は「発作が起きたときに治す」だけでは足りません。
症状がないときも気道には炎症がくすぶっており、それを抑えるための長期管理が非常に重要です。
抗アレルギー薬の内服と、必要に応じた吸入ステロイド薬の使用をバランスよく行い、
再発や合併症を防ぎ、お子さんの毎日を守っていきましょう。
当院では、呼気NO(FeNO)測定や丁寧な吸入指導を行いながら、個々に応じた治療プランをご提案しています。
FeNOについてはこちら
ご不安な点があれば、いつでもご相談ください。