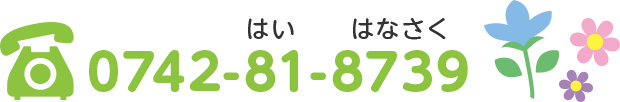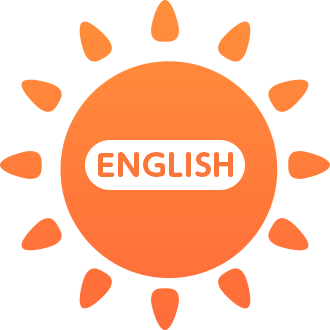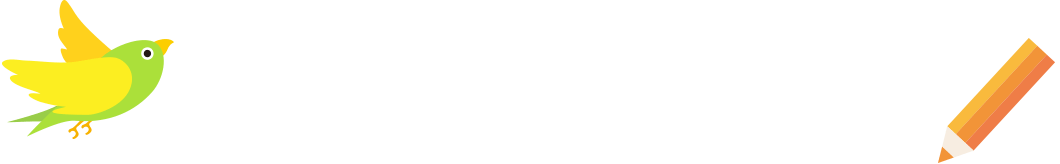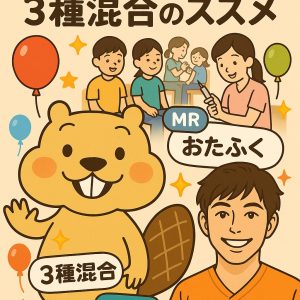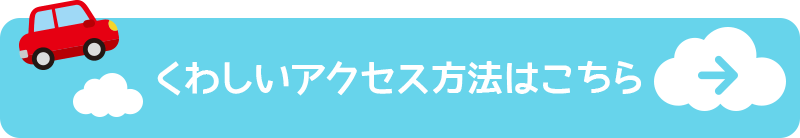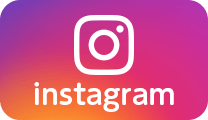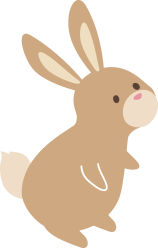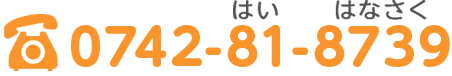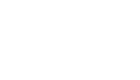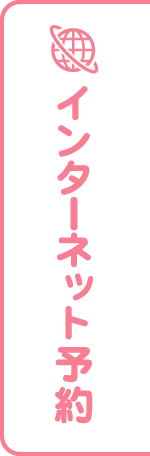2020.05.27
最終更新日: 2025年04月23日
年長さんのワクチンはどれ?3種混合のススメ
年長さんは小学校に入る前の大切なワクチン接種のタイミングでもあります。
このページでは小学生になる前(年長さん)に、済ませておきたいワクチンについて書きたいと思います。
目次
年長さんでうてるワクチンはどれ?
この時期に打てるワクチンは
- MR(麻疹・風疹)
- おたふく
- 三種混合
- ポリオ
となります。
🌸 定期接種で必ず受けてほしいワクチン
MRワクチン(麻しん・風しん)第2期
MRワクチン(麻しん・風しん)ってどんなワクチン?
MRワクチンは、麻しん(はしか)と風しんを一度に予防できる、とても大切なワクチンです。
年長さんの時期(小学校入学前)に受ける「第2期」は、
1歳で受けた1回目の接種でついた免疫をしっかりと強化するために行います。
麻しん(はしか)ってどんな病気?
高熱、咳、目の充血、全身に出る発疹…と、とてもつらい感染症です
特に小さなお子さんでは、肺炎や脳炎になるリスクもある重い病気です
空気感染するので、うつる力がとても強いのが特徴です
海外からの流行が時々起きており、ワクチンを打っていないと集団感染につながることもあります
風しんってどんな病気?
発熱や発疹などの比較的軽い病気と思われがちですが、
妊娠初期の女性が感染すると、生まれてくる赤ちゃんに障がいが起こるリスクがあります(先天性風しん症候群)
そのため、風しんをなくすことは、子どもたちだけでなく、社会全体にとっても大切なことなんです。
💉 MRワクチンの効果について
1回目+2回目の2回接種で、ほぼ100%に近い予防効果が期待できます
麻しんも風しんも、**ワクチンで防げる病気(VPD)**です
2回目を受けていないと、免疫が弱まってしまうこともあります
👨⚕️ まとめ
✅ 年長さんでのMRワクチン(第2期)接種は、入学準備のひとつ!
✅ 大人になっても守ってくれる大事な免疫をつけるチャンスです
🌿 任意だけど、受けておくと安心なワクチン
おたふくかぜ(ムンプス)ワクチン
1歳で1回目を接種していても、実は2回接種しないとしっかり予防できないと言われています。
まだ2回目を打っていないお子さんは、このタイミングでの接種をおすすめしています。
💉おたふくかぜワクチンの効果について
「おたふくかぜ」は、多くの子どもがかかる感染症ですが、実は**「ただの風邪」ではありません**。
ほっぺが腫れて痛いだけで済めばよいのですが、実はこんな合併症が起こることがあります。
🧠 主なおたふくかぜの合併症
無菌性髄膜炎(ずいまくえん)
→ 脳や神経の膜に炎症が起きる病気。高熱・頭痛・吐き気などが出ます。難聴(なんちょう)
→ 片方の耳が聞こえにくくなることがあります。ごくまれに治らないこともあります。睾丸炎(こうがんえん)・卵巣炎
→ 思春期以降にかかると、精巣や卵巣に炎症が起き、将来の妊娠や不妊のリスクになることも。
💉 ワクチンで防げるの?
おたふくワクチンを2回接種することで、
発症を約9割防ぐことができます
合併症(とくに無菌性髄膜炎・難聴など)のリスクを大きく減らせます
1回だけでもある程度の効果はありますが、2回目で免疫がよりしっかりつきます。
👨⚕️ まとめ
おたふくかぜワクチンは、ただ「病気をうつさないため」だけでなく、
お子さん自身の将来の健康(聴力や妊孕性)を守るため
大事な合併症を予防するため
に、とても大切なワクチンです。
難聴などの合併症を起こすと治療は非常に困難です。
防ぐ方法はワクチンしかありません。
自然にかかれば良いなんて思わないで、是非接種をご検討ください!
3種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風)
3種混合が年長さんの時期に接種がおすすめな理由
乳幼児期に受けた4種混合(DPT-IPV)ワクチンの効果は、年長さんの頃には百日せきに対して少しずつ弱くなってきます。
でも、中学生になるときの定期接種(2種混合)には百日せきが含まれていません。
ですので、「百日せきをもう一度しっかり防ぐために」、
年長さんの時期にこの3種混合ワクチンを追加で接種するのがすすめられています。
💉百日せきに対するワクチンの効果について
百日せきって、聞いたことはあるけど「昔の病気じゃないの?」と思われるかもしれません。
でも実は今も定期的に流行することがある感染症で、特に赤ちゃんにとってはとても怖い病気なんです。
🤧 百日せきってどんな病気?
はじめは風邪のような症状ではじまり、次第にコンコンコン…と連続する強い咳が出るようになります。
咳の後に「ヒューッ」と息を吸い込む音が出るのが特徴です(英語で“whooping cough”と呼ばれる理由です)。
夜中に咳き込んで眠れなかったり、咳き込んで吐いてしまうこともあります。
特に0歳の赤ちゃんでは、無呼吸(息が止まる)になったり、入院が必要になったりすることもある、
命に関わることのある、油断できない病気です。
💉 ワクチンの効果は?
百日せきのワクチン(3種混合・4種混合)は、以下のような効果があります:
感染を防ぐ/発症を軽くする
重症化(無呼吸や入院)を防ぐ
周囲の赤ちゃんや高齢者にうつすリスクを減らす
⏳ でも、ワクチンの効果は時間とともに弱まります
乳児期に4回接種する4種混合ワクチンはとてもよく効くのですが、
5年くらいで免疫が落ちてしまうため、小学校入学前の年長さんでの3種混合ワクチンの追加接種がすすめられています。
また、中学生での2種混合ワクチン(DT)には百日せきが含まれていないため、免疫がさらに落ちてしまいます。
👨⚕️ まとめ
百日せきワクチンは、
お子さん本人が重い咳で苦しまないため
まわりの赤ちゃんにうつさないため
将来の集団生活(学校・部活)で流行を広げないため
に、とても大切な予防接種です。
特に、年長さん〜小学校低学年のタイミングでの追加接種が安心につながりますよ。
年長さんを過ぎてしまっている場合は?
このブログを読んで、
「上の子、まだ3種混合を打ってなかったかも…!」
と気づかれた方もいらっしゃるかもしれません。
ご安心ください😊
年長さんを過ぎていても、3種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風)は接種可能です。
ただし、11〜12歳になると定期接種として2種混合(DT)ワクチンを打つことになります。
そのため、3種混合と2種混合の接種時期が近すぎない方が理想的です。
当院では、
8歳くらいまでなら、3種混合ワクチンの接種をおすすめしています。
9歳以降の方で、百日せきの免疫が気になる場合には、2種混合をスキップして3種混合を接種するという選択肢もあります。
ただし、2種混合は公費(無料)で受けられるので、「もったいないなぁ」と感じるかもしれません。
🌟 できれば、年長さん〜小学校低学年のうちに3種混合ワクチンを受けておくのがベストです!
ポリオワクチン(不活化ポリオ:IPV)
不活化ポリオは通常4回接種が必要ですが、これは4種混合に含まれていますので、
4種混合をスケジュール通りに打っている場合は、4回接種が完了しています。
ただ、免疫が低下していくため、海外ではポリオは4回以上接種します。
現時点では日本での発生はありませんが、海外に行かれる場合には免疫が不十分ですから、接種が望ましいといえるでしょう。
転勤等で長く住まれる場合には追加接種を求められることもよくあります。
該当する方はチェックしておきましょう。
ポリオって?ワクチンで防げる病気です!
ポリオ(急性灰白髄炎)は、かつては日本でも多くの子どもたちがかかっていた病気です。
ウイルスが神経に入ると、**手足のまひ(麻痺)**が起こることがあり、
一度まひが出てしまうと元に戻らないこともあります。
今は日本ではほとんど見られなくなりましたが、海外ではまだ流行している地域もあり、油断できません。
💉 ポリオワクチンの効果は?
感染をほぼ完全に防ぐ(発症予防率 約95%以上)
まひを防ぐだけでなく、周囲への感染拡大も防止できます
日本では、生後2か月から始まる**4種混合ワクチン(DPT-IPV)**の中に含まれています。
4回接種でしっかりと免疫がつきます。
🧸 まとめ
ポリオは、まれだけどかかると重い病気です。
しっかりとワクチンを受けておくことで、将来にわたって安心できます。
💉「3種混合とポリオを打つなら、4種混合じゃダメなの?」と思った方へ
ここまで読んでいただいて、
「3種混合(DPT)と不活化ポリオ(IPV)を打つなら、4種混合(DPT-IPV)で一緒に打てばいいのでは?」
と思われた方、いらっしゃいますよね?

注射の回数はできるだけ少ない方がいいし、痛いのは一回でも減らしたいものです。
でも、残念ながら4種混合ワクチンは使えないんです。
どうしてかというと…
4種混合ワクチンは、乳幼児期に4回接種することだけが承認されているワクチンです。
年長さんの時期に接種するのは「5回目」にあたるため、このタイミングでの4種混合は認められていないのです。
ちょっと納得いかない感じもあるかもしれませんが、
この時期に百日せきやポリオの免疫を強化したい場合は、
👉 **3種混合ワクチン(DPT)**と
👉 **不活化ポリオワクチン(IPV)**を
別々に接種する必要があります。
まとめ
MRワクチン第2期は定期接種として必ず受けましょう。
おたふくかぜワクチンは2回接種が推奨されています。未接種の場合はこの時期に接種を検討しましょう。
3種混合ワクチンは百日せきの免疫を維持するため、年長児の時期に追加接種が推奨されています。
不活化ポリオワクチンは、海外渡航予定がある場合に追加接種を検討しましょう。
母子手帳を確認し、接種状況を把握することが大切です。
お気軽に当院にご相談ください。一緒にスケジュールを確認させていただきます。